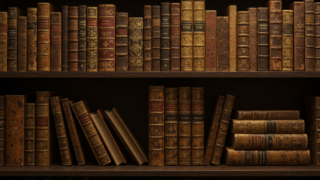 読書
読書 読書中に耳栓を使う人は少ない?意外な事実とその理由
読書中に周囲の音を遮るために耳栓を使用する人は少ないのか、多くの人はそうしていないのか、という疑問に答えるべく、読書と音の関係、耳栓を使うことのメリットやデメリットについて考えてみましょう。読書中の音と集中力読書において周囲の音は、集中力を...
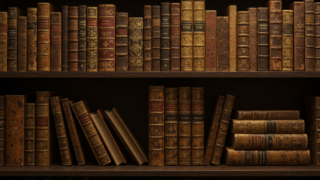 読書
読書 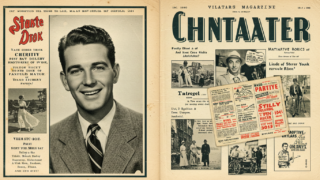 読書
読書 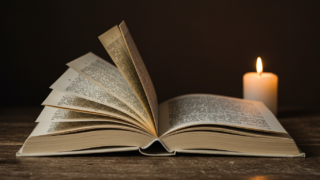 読書
読書  読書
読書 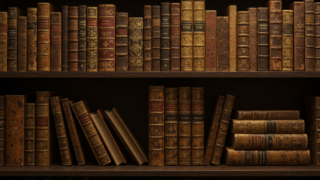 読書
読書  読書
読書 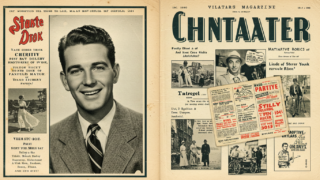 読書
読書 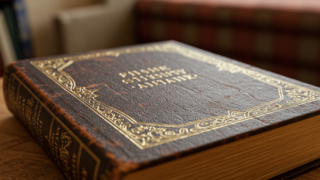 読書
読書 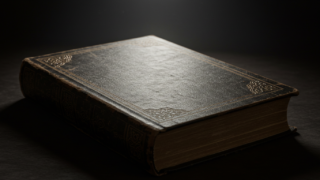 読書
読書  読書
読書